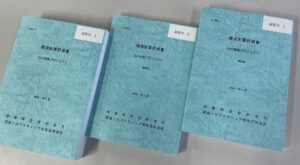「介護の社会化」を求めて 3月議会一般質問①
立川市議会の2025年第1回定例会(3月議会)の本会議一般質問が21日に始まり、私は2番手で登壇しました。今回は①介護の社会化②かまどベンチ③避難所運営マニュアル④有機フッ素化合物PFASによる地下水汚染⑤オスプレイーの5つの大項目について質問の準備をしました。今回特に力を入れたのは、介護の問題。【介護の社会化を実現するには】【介護の人材確保】【介護事業所への支援】【介護認定】【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の在り方】【必要な介護サービスを受けられるには】など概ね下記のように述べ、立川市が取り組むべきことについて質し、提案・要望しました。
◎ 「介護の社会化」を実現するには!(介護保険を立て直す、自治体でできることは)
 介護保険制度がスタートして、今年で25年。私たち生活者ネットワークは長年「子育て、介護は社会の仕事」と訴えてきました。介護保険制度が2000年に始まった際には「介護の社会化」がいよいよ実現すると期待も膨らみました。しかし四半世紀たった今、それが本当に実現したのか。ある程度実現したとして、それを今後も維持し、充実させていけるのか。「今、介護保険制度は崖っぷちに立たされている」と言われています。今年が「介護崩壊元年だ」という学者もいます。介護事業者の倒産・閉鎖が過去最多を記録し、介護人材の不足も深刻化する一方で、保険料の基準額全国平均は2000年度に比べ既に2倍以上。大阪市では月9千円を超えています。そんな中で保険料を上げないために給付抑制をするという「介護保険のジレンマ」が生じ、極めて使いにくい制度になっているとも言われています。こうした現状を本市としてどのように捉えているのか、お示しください。
介護保険制度がスタートして、今年で25年。私たち生活者ネットワークは長年「子育て、介護は社会の仕事」と訴えてきました。介護保険制度が2000年に始まった際には「介護の社会化」がいよいよ実現すると期待も膨らみました。しかし四半世紀たった今、それが本当に実現したのか。ある程度実現したとして、それを今後も維持し、充実させていけるのか。「今、介護保険制度は崖っぷちに立たされている」と言われています。今年が「介護崩壊元年だ」という学者もいます。介護事業者の倒産・閉鎖が過去最多を記録し、介護人材の不足も深刻化する一方で、保険料の基準額全国平均は2000年度に比べ既に2倍以上。大阪市では月9千円を超えています。そんな中で保険料を上げないために給付抑制をするという「介護保険のジレンマ」が生じ、極めて使いにくい制度になっているとも言われています。こうした現状を本市としてどのように捉えているのか、お示しください。
【介護の人材確保】今年2025年は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、今後、介護ニーズが一層高まると予測されますが、介護の現場は重労働でありながら低賃金であるため、慢性的に人材不足となっています。3年ごとに行われる介護報酬改定でも、介護サービスに対する基本報酬が引き上げられることはほとんどなく、労働組合の日本介護クラフトユニオンが1月末に公表した調査結果によれば、介護職員の昨年7月の基本給は全産業平均より6万4489円低かったということです。
政府は処遇改善加算の引き上げなどによって、賃金の底上げを図ろうとはしていますが、ヘルパー不足によって介護の「家族回帰」が進み、ヤングケアラーやダブルケア、老老介護、さらにはビジネスケアラーの介護離職の問題も深刻化しています。経済産業省の推計ですが、根本的な対策が進まないと、介護離職者やビジネスケアラーが最も増えると予想される2030年には、介護と仕事の両立の難しさ等による経済損失が、約9・2兆円に上ると試算されています。「介護の社会化」を維持・充実させるためには、国がしっかりと介護報酬などを上げていくべきですが、保険者・運営主体である立川市としてもやれること、やるべきことがあると思います。
市においても、2027年度にスタートする「第10期介護保険事業計画」に向け、「介護人材等確保のための検討会議」を設置し、介護人材確保策を検討していただいているところですが、人材不足は既に待ったなしの状態です。介護福祉士の資格取得については既に支援していただいているわけですが、それに加えてケアマネージャー等の受験料など助成することはできないのか伺います。
淑徳大学の結城康博教授はその著書『介護格差』の中で、介護人材の不足、特にヘルパーの不足を解消するため、ヘルパーを市町村の終身雇用の公務員として採用し、市町村立の訪問介護事業所を創設するべきだとの論を展開されています。人口減少社会で、全産業で人手不足が深刻化していくわけですから、こうしたヘルパーの公務員化も一つの方策だと思いますが、市のご見解を伺います。
【介護事業所への支援】人材不足や基本報酬引き下げ、物価高などにより、倒産や閉鎖に追い込まれる介護事業所が増え、東京商工リサーチの調査によれば、昨年倒産した介護事業者は過去最多の172件。倒産と休廃業合わせて784件。このうち、訪問介護の事業者は529件に上り、これも過去最多の倒産・休廃業件数だということです。倒産や閉鎖によって、要介護者が、それまで受けていた必要な介護サービスを受けられないという事態も生じていると聞きます。立川市においても具体的な事例があるのでしょうか。
今後も倒産や閉鎖が増えていくとなれば、制度はあってもサービスを利用できない要介護者もますます増えていくことになると思われます。市の独自財源で介護事業所への報酬を上のせている自治体(徳島県三好市)もあると聞きます。本市においては本年度「介護サービス事業者物価高騰重点支援事業給付金」の給付などにより、事業者支援をしていただいているわけですが、ぜひ来年度以降も事業所支援の施策をお願いしたいと思いますが、お考えをお聞きします。
 【介護認定】介護認定については、全国的に認定までの日数がかかっているという話を聞きますが、本市の状況を伺います。入院している方が退院後の準備をするときに、認定が降りていないと自宅で受け入れる準備もままならなくなり、困ってしまうという話を以前から聞いています。時間がかからないよう改善策をお願いします。
【介護認定】介護認定については、全国的に認定までの日数がかかっているという話を聞きますが、本市の状況を伺います。入院している方が退院後の準備をするときに、認定が降りていないと自宅で受け入れる準備もままならなくなり、困ってしまうという話を以前から聞いています。時間がかからないよう改善策をお願いします。
【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の在り方】介護の現場は大変な状況に陥っているわけですが、その中でも強く懸念されるのは認知症の方のケアです。「認知症の人が尊厳を保持し、希望を持って暮らすことができる」ことなどを目的とした「認知症基本法」が2023年に制定され、昨年12月には基本計画も閣議決定されましたが、政府は2027年の介護保険の制度改定で、認知症の初期から中期に当たる、手厚いケアが必要となる要介護1と2の高齢者について、訪問介護と通所介護を市町村の総合事業に移管しようとしています。移管された場合、人手が集まらず生活援助が成り立たなくなる、生活援助は失われてしまうと懸念されています。私も認知症基本法の目的や理念にも逆行するのではないかと危惧しています。現状、要介護1と2の方は何人いて、総合事業に移管された場合のメリットおよびデメリット、また移管の動きそのものを市としては現在どう考え、捉えているのかお聞かせください。仮に総合事業に移管された場合、立川市ではきちんと対応できる体制となっているのか、どのような対応・対処が必要となってくるのかお考えをお伺いします。総合事業の開始によって要支援者のサービスの自治体間格差も生じていると言われています。国において総合事業そのものも見直す必要があると考えますが、市としての見解を伺います。
【必要な介護サービスを受けられるには】政府内では、2027年の制度改定に向けて、サービス利用料の2割負担の標準化やケアプランの有料化など、利用者負担を引き上げる方向で検討が進められています。これが実施された場合、格差が拡大し、経済的に苦しい高齢者がサービスを受けること自体を諦める、必要な介護を受けられないような状況を招くことにもなりかねません。利用者負担の引き上げないよう、これも国に求めていただきたいと思いますが、見解をお伺いします。 介護の社会化を更に推進していくためにも、ぜひ立川市から率先してやっていただくようお願いします。